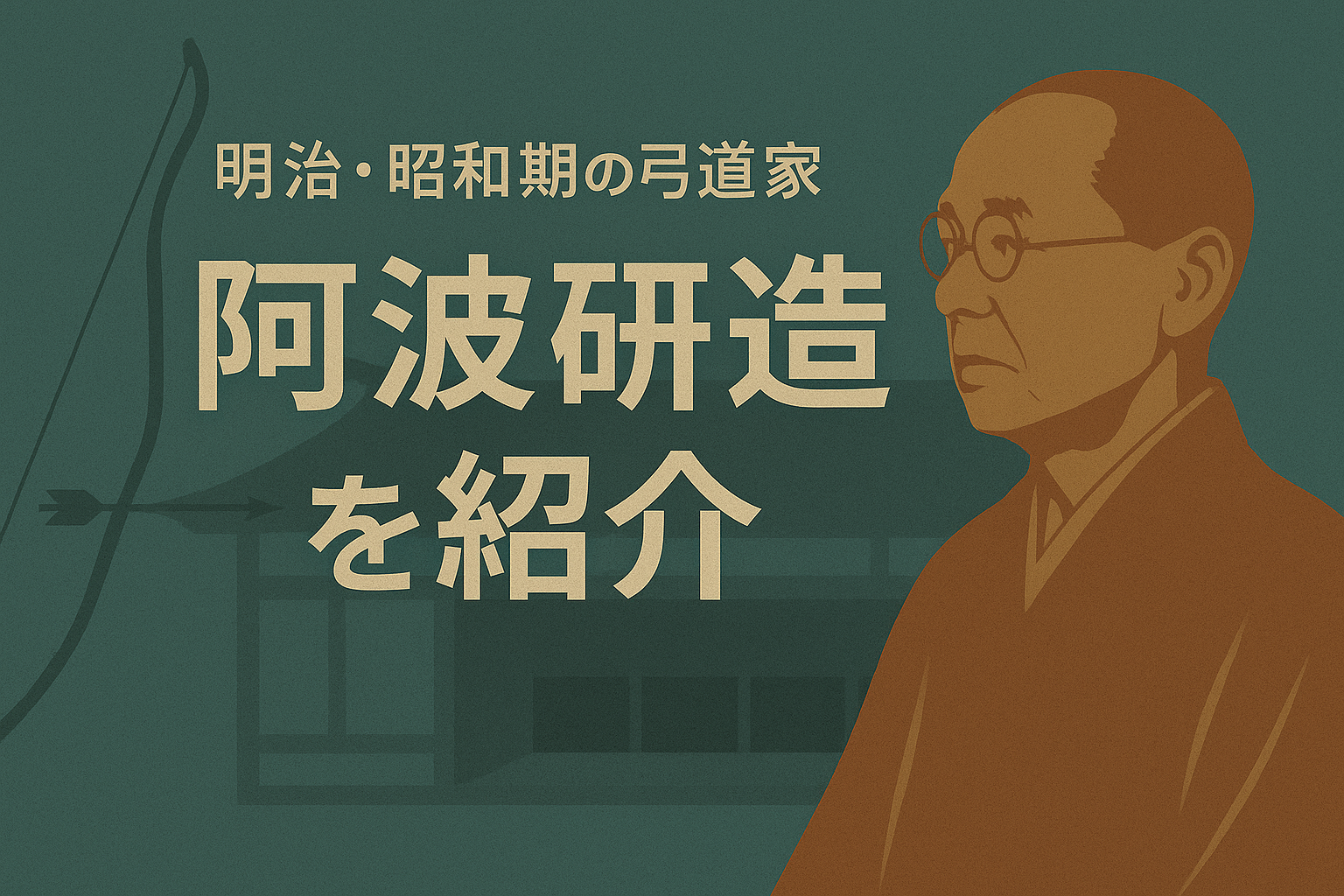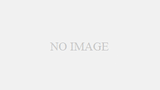弓の長い歴史の中で、名を残す弓道家は数多くいます。今回はその中でも、明治から昭和期にかけて活躍し、弓道の思想に大きな影響を与えた阿波研造についてご紹介します。
阿波研造の経歴
- 1880年(明治13年)、宮城県桃生郡河北町(旧大川村)の麹業佐藤家の長男として生まれる。
- 20歳:石巻仲町の麹業・阿波家の婿養子となる。
- 21歳:雪荷派弓術師範・木村辰五郎に入門。
- 23歳:石巻に講武館を創設。弓・剣・柔道・居合・抜刀術・薙刀を指導。
- 30歳:仙台市に転居し弓道場を開館。竹林派弓術師範・本多利実に入門し、市内の学校でも師範を務める。
- 34歳:大日本武徳会より三等師範の免許を授与。「無箭(むせん)」「無弦(むげん)」「無弓(むきゅう)」などと号す。
- 1918年(大正7年):仙台市に道場を新設。
- 1920年(大正9年):「凡鳳(ぼんぽう)」と号し、大日本武徳会教士、大日本弓道会八段となる。
- 1924年(大正13年):ドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルが入門。
- 1927年(昭和2年):大射道教を創建。「見鳳(けんぽう)」と号し、武徳会範士となる。
- 1930年(昭和5年):仙台市に大射道教本部道場を建設し、「宏鴻(こうこう)」と改号。
阿波研造の思想
阿波研造は、単なる技術にとどまらず、射における精神性や哲学を重視しました。八段のころには「不発の射」「宇宙と射と一体」といった言葉を用い、深い射の境地を説いています。
1923年(大正12年)には「一射絶命」「射裡見性(しゃりけんしょう)」を唱え、「我れ弓道を学ぶこと20余年、徒に形に走り、その神を忘れしこと、近年初めて自覚せり」との言葉を残しています。
大日本武徳会とは
大日本武徳会は、1895年(明治28年)に京都で設立された団体で、武術教育を通じた精神鍛錬と武道の体系化を目的としました。1919年(大正8年)には各武術の名称が整理され、弓術は「弓道」となります。他にも、剣術と銃剣は剣道、柔術は柔道と改められました。
戦後、GHQの指示により、1946年(昭和21年)に解散しています。
まとめ
阿波研造は、弓道を単なる技術やスポーツとしてではなく、精神と一体となった「道」として高めた人物です。彼の教えは現代にも多くの影響を与えており、特に西洋に弓道を紹介したオイゲン・ヘリゲルとの関わりも含めて、その功績は今も語り継がれています。