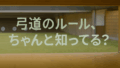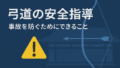毎年1月、京都の蓮華王院本堂(三十三間堂)で開催される「通し矢(とおしや)」。弓引きにとって一度は訪れたい特別な行事です。かつての弓引き達がしのぎを削った舞台で矢を放つ姿には、日本の伝統文化の美しさが宿ります。この記事では、通し矢について解説します。
通し矢の歴史
通し矢とは、三十三間堂の軒下にある長廊下を射通す行事のことです。起源は保元の乱の頃(1156年頃)に遡りますが、一昼夜射通した数を競う「大矢数」が1600年代に流行し、京都の蓮華王院本堂だけでなく、通し矢用に用意された江戸三十三間堂、東大寺大仏殿西回廊でも開催されました。
新記録達成者は天下一を名乗ることができたため、多くの弓引きが記録に挑みました。後に紀州藩と尾張藩の一騎打ちの様相を呈すほど藩をあげた行事となりました。
「矢数帳」には、通し矢法を伝承した〈日置六流(へきろくりゅう)〉の江戸期の試技者氏名、月日、矢数などが編年で書き留められています。最高記録は、貞享3年(1686)4月、紀州藩士の和佐大八郎※(試技年齢は18歳)の総矢13,053本、通し矢8,133本だそう。強靭な身心にしてこそ可能な凄絶な競技だったことが窺えます。
競技の種類には、時間を決めて射通す「大矢数」「日矢数」「夜矢数」と、矢数を決めて射通す「千射」「五百射」「百射」がありました。
三十三間堂の距離
- 京都蓮華王院 全長:121.7m、高さ:4.5-5.3m、幅:2.36m
- 江戸三十三間堂 全長:122.0m、高さ:5.0-5.6m、幅:2.69m
- 東大寺大仏殿西回廊 全長:106.8m、高さ:3.8-4.1m、幅:2.10m
※トピックス|吉見順正
和佐大八郎の先輩にあたる名士に吉見台右衛門経武という徳川時代中期における紀州藩の藩士がいます。この人物は後に仏門に入り、吉見順正を名乗っています。吉見順正の遺訓「射法訓」は、「礼記射義」と並ぶ現代弓道の基礎的な教えです。この2つの教えはさまざまな道場に掲示されています。
現代の通し矢
江戸時代前期に最盛期を迎えた、行事としての通し矢は現在行われていません。現在は、京都蓮華王院本堂の境内で京都府弓道連盟主催の「大的全国大会」が開催されています。
大的全国大会は、成人の日にちなんで行われるものです。矢数は一手、距離は遠的の60m、対象は弓道連盟所属の成人です。全国規模の大会ですが予選がないため多くの参加者が集います。
新成人が晴れ着や袴姿で弓を引く光景はメディアにもよく取り上げられ、伝統と現代をつなぐ弓道大会として年々注目度を高めています。
大学生はぜひ通し矢に参加を
三十三間堂という歴史的な場所で射を行う経験は、弓引きにとって一生の思い出になります。寒空の中、的を見据える集中力、矢を放つ静かな緊張感、それを見守る観客の気配――すべてが特別な空気を作り出します。
また、成人式に合わせて開催されることから、「人生の節目を祝う儀式」という側面も強く持っています。大人としての新たな一歩を、伝統の中で踏み出せることは、現代ではなかなか得られない貴重な体験です。
申し込みは先着です。詳細は京都府弓道連盟ホームページを確認してください。
観覧の際のポイントと楽しみ方
通し矢は誰でも観覧することができますが、いくつかの注意点があります。まず、早朝からの開催でとても寒いため、防寒対策は必須です。京都の1月は冷え込みが厳しく、風が吹き抜ける境内では足元から冷えます。帽子・手袋・ホッカイロなどを持参して、快適に観覧できる準備をしましょう。
観覧エリアは限られているため、良い場所を確保するには早めの到着が望ましいです。写真撮影は可能ですが、他の観覧者の迷惑にならないよう配慮を忘れずに。
観覧の魅力は、一人ひとりの射に込められた真剣な気迫を間近で感じられることです。大会とはいえ派手な演出はなく、あくまで静かに粛々と行われます。そこに、弓道の美しさと武道としての精神が凝縮されているのです。
まとめ
現代の三十三間堂の通し矢は、ただの大会にとどまりません。弓道の伝統と格式、若者たちの成長の証、そして日本文化の奥深さを感じられる稀有な行事です。出場を目指すもよし、観覧を楽しむもよし。弓道に関心のある方なら、きっと心を打たれる体験になるはずです。次の冬、京都を訪れてその空気に触れてみてはいかがでしょうか。