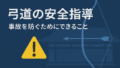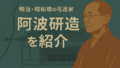弓道の大会を見ていると、「構え方が違う」「所作に違和感がある」と感じたことはありませんか?それは、弓道の「流派」の違いからくるものです。この記事では、弓道における流派とは何か、代表的な流派、そして現代弓道におけるその位置付けについて解説します。
流派とは何か
弓道における「流派」とは、弓の引き方や所作、精神性などにおいて独自の体系を持つ伝統的な教えのことを指します。これらの流派は、歴史的な背景や地域性、師弟関係などによって形成され、長い年月をかけて受け継がれてきました。流派によって、構え方や打起しの方法、射法の考え方などに違いがあります。
主な流派とその特徴
本多流
本多流は、日置流尾州竹林派を基に本多利実が正面打起しに改めて創設した流派です。正面打起しを採用し、武射系の特徴を持ちます。大三を取ることが特徴で、実戦的な射法を重視しています。
小笠原流
小笠原流は、礼法を重視した流派で、正面打起しを採用しています。儀礼的な所作や精神性を重んじ、射法においても礼儀や美しさを追求します。宮中の儀式や神事などでも用いられることがあります。
日置流
日置流は、武射系の代表的な流派で、斜面打起しを採用しています。実戦的な射法を重視し、矢勢や貫通力を追求します。日置流には多くの分派が存在し、それぞれに特徴的な射法があります。
流派の統一と弓道連盟
全日本弓道連盟が昭和28年に弓道の指針と規範となるものを制定するために「弓道教本」第一巻を作成しました。様々な流派の長所を生かして現代弓道の指標とし、特定の流派に所属しなくとも、弓道の大綱を学ぶことができるようになりました。射法八節を定め、正面打起しと斜面打起しの両方法を採用し、礼記射義、射法訓、および最高目標としての真善美を掲げ、これまでの弓の文化を尊重し継承しつつ、新たな弓道を定義づけました。これにより、体配は全国的に統一され、弓射の内容も一段と進歩しました。
まとめ
弓道の流派は、弓術の歴史と武士文化の名残です。現代の弓道は、ある程度「標準化」されていますが、型の美しさや精神性を学ぶためには流派の理解も大切です。競技だけでなく、「武道」として弓道を深めるためには流派を学ぶ価値があります。